2025/07/30

例年盛り上がるアジア最大級の書籍の祭典、香港ブックフェアが今年も大盛況のうち幕を閉じました。一週間にわたって繰り広げられ、100万人ちかくの来場者を動員するという出版業界の一大イベント。
とはいえ、フェア内で開催されるのはお堅いイベントばかりではありません、今年はポップスターMirrorのメンバー、タイガー・ヤウ(邱傲然)のトークショーや女優のナタリー・ン(吳文忻)のサイン会など、芸能界からのゲストによる華やかな催し、新作書籍の発表会なども行われました。
香港ブックフェアは毎年、海外からも著名なゲストが招聘されることでも知られています。今年、日本からは作家の九段理江さんが招かれ、芥川賞受賞作品『東京都同情塔』についてのトークを行いました。35回を迎えたブックフェアと偶然にも同じ年だという九段さんは香港メディアの記者や香港人ファンを前に、にこやかに質問に応えてくれました。九段さんは作品にAIを使用することで知られています。ここではAIと小説作品との関係についてなど、トークの内容をダイジェストでお伝えします。

作家になった経緯
小さい時から文章が好きでしたが、ウィンドウズ95(当時主流だったパソコンソフトウェア)が出た5歳の時からわたしはパソコンを使うようになって、文章を書き始めました。小さい時から書くこととテクノロジーというのはわたしにとって切り離せない存在なんです。
わたしが小説を書くモチベーションは、物語、ストーリーを書きたいということが起点ではなく、テクノロジーを使いたいがために頑張ってお話を作り出してるっていう感じなんです。
『東京都同情塔』について
2021年東京オリンピックの開催が決定した際、東京にはザハ・ハディドの設計によるスタジアムが建設されることになっていました。最終的には建築されることはなかったんですが。この作品ではザハ・ハディド建設が実現していたら、というパラレルワールドを描いています。主人公はザハ・ハディドに強い思いを抱く女性の建築家。本当は建築のことを考えを巡らせたいのに、その建築物に付けられた名前、その言葉が気になってしまう。そういうお話です。
今、日本の状況として、従来ある言葉を英語由来のカタカナとして言い換えてしまうということが多く行われています。カタカナにすることで本質的なものを消そうとしている、隠そうとしている、そういう目的を持って外国語を頻繁に使うのではないかと思うんです。例えば「母子家庭」を「シングルマザー」と言い換えることで、意味がフラット(ニュートラル)になります。ネガティブな印象を避けたかったり、他人を傷つけることを回避したりという、ポリティカルコレクトネスを目指す日本人の傾向と合致するんです。
 香港の金融街にも、ザハ・ハディド・アーキテクツが設計した36階建てのThe Hendersonがある(写真左から二番目の建物)。2024年撮影
香港の金融街にも、ザハ・ハディド・アーキテクツが設計した36階建てのThe Hendersonがある(写真左から二番目の建物)。2024年撮影
なぜ、ザハ・ハディド?
彼女はアンビルドの建築家として知られているからです。アンビルドというのはun-built つまり「建築されない」建築家という意味なんですが、これが小説のコンセプトととても似ていると思うからです。アンビルドというのは実際には建っていないけれども、思想は残っているというものです。小説も同様で、実際には起こっていないフィクションなんですけれども、それを読んだ人の頭の中には存在するものです。それをこの本の中で表現したかったんです。
実は(ザハの建築は)香港でも過去に建築が予定されていたのに、実現しなかったものがあるんです。香港島のピークに彼女の手による建築物が建てられる予定でした。
AIを小説に使うことについて
もともと戦略的に、計画的にAIを小説の中に組み込もうと思ったわけではないんです。プライベートでAIを使っているときに、AIが使っている言葉に奇妙な感触を覚えたんですね。人間を巧みにコピーしたものでありながらも、少し非人間的な言葉。これを小説の中で表現したら、面白い化学反応が起きると思いました。
AIはツールである、あるいはコラボの相手(共同作業者)である、という考え方はわたしには当てはまらないです。AIと人間、お互いの足りないところ、弱いところを補い合う、サポートし合うという感覚です。例えばザハ・ハディッドは自分の創造性だけでなく、コンピュータを積極的に使用しています。そうすることで人間にはできなかった建築デザインが実現されています。わたしがやりたいのがまさにそういうことで、人間だけでは思いつかなかったこと、人間の限界を超えるようなこと、まだ見たことがないものを作りたいという欲求を持っています。テクノロジーを使うことによって自分の動力以上のものを見てみたいという好奇心があります。
AIと言葉について
英語の言葉を日本語(カタカナ表記)に輸入するときに、意味がフラット(ニュートラル)になると言いました。今、日本の人たちがポリティカルコレクトネス(差別や偏見がある、あるいはあると疑われる可能性がある表現や行動を回避すること)を重視するあまり、AIが発する言葉と人間の言葉がどんどん似てくるという状況にあると思います。どちらもニュートラルになっていく、そんな状況を小説の中で表現したかったため、AIは(わたしの)小説の中では重要な役割を担っています。例えば、ChatGPTの回答がそのまま小説の一部に使っている部分があります。
小説におけるAIの役割について
小説においてAIがどんな使われ方をしていくか、については作家次第だと考えます。色々なタイプの作家がいますので……。例えば、作品の登場人物の名前や企業の名前をAIに考えてもらうという作家の方がいます。わたしはその部分は自分で考えるのが得意だし好きなので、自分で考えたいです。つまり、AIの役割はそれぞれ作家の苦手な部分を補うっていうことだと思うんです。作家自身が自らの弱点を理解して、どうAIにサポートしてもらうのかということを知るのが大切だと思います。
AIの言葉にコピーライト(著作権)はあるのか
それは疑問に思っています。同時に考えるのは、近年、小説や本を求める人が少なくなっていて、本を読むより動画を観たりすることが多くなっている中で、なぜ小説ばかりにコピーライトの件など、厳密性を求めるんだろうかと。
さわやかでおっとりした雰囲気の九段さん。質問に回答する時の表情はにこやかで穏やか。まるでカフェで友人と話しているようなリラックスした様子ですが、回答の内容は理路整然としていてシャープ。刺激的なものでした。文章を書くことを毎日絶やしたことがないという彼女、今後の作品も楽しみです。
取材・文 紅磡リンダ(編集部)

Hong Kong LEI (ホンコン・レイ) は、香港の生活をもっと楽しくする女性や家族向けライフスタイルマガジンです。
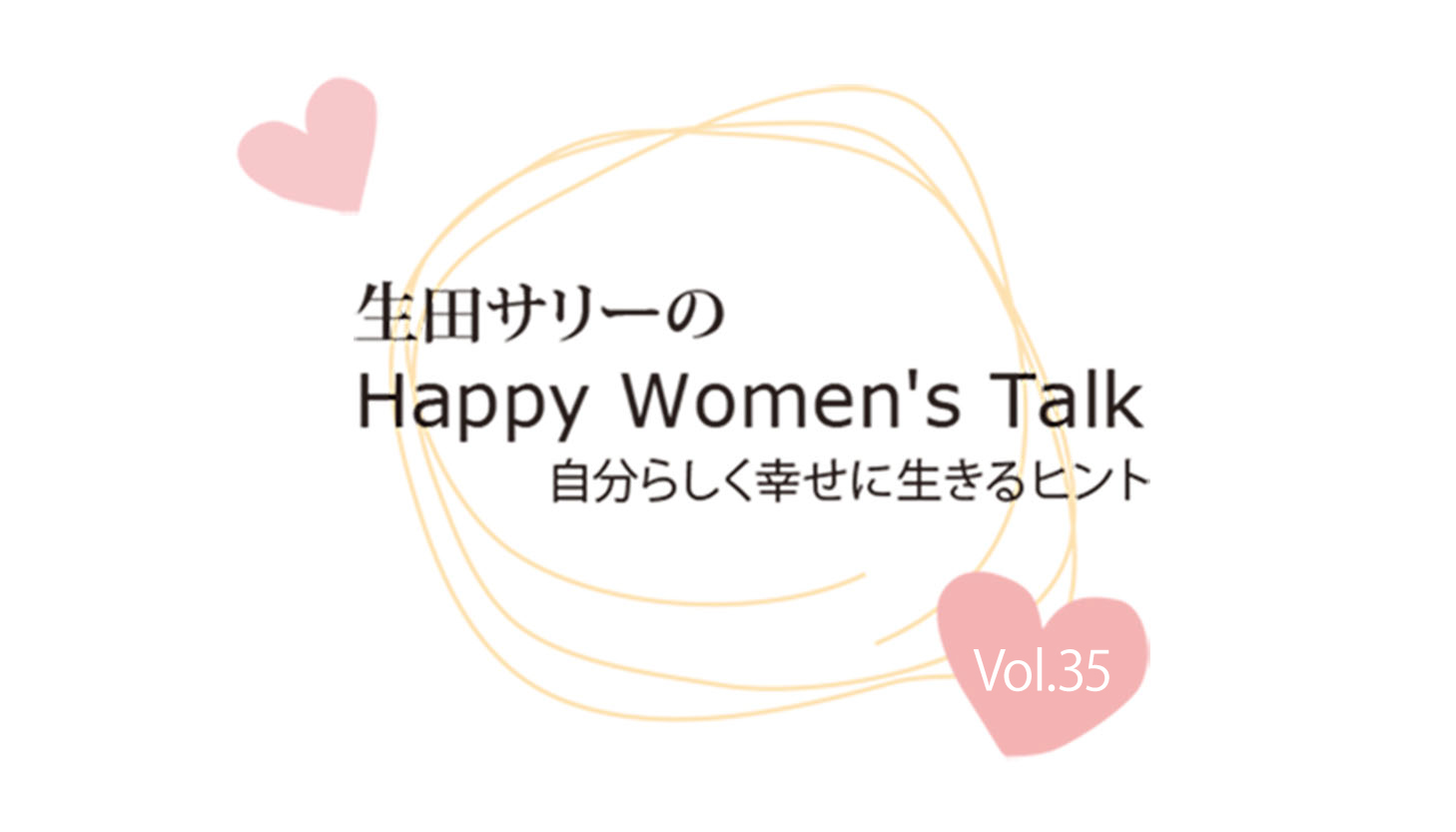



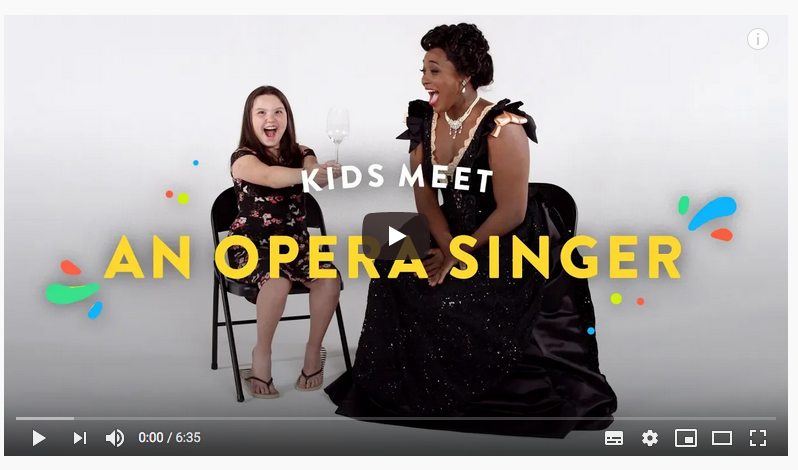
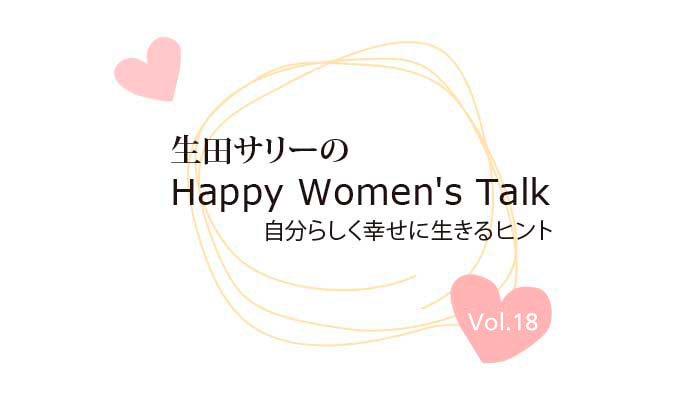
コメントをありがとうございます。コメントは承認審査後に閲覧可能になります。少々お待ちください